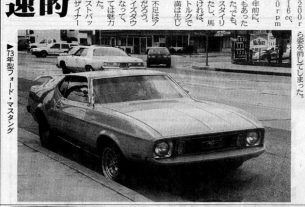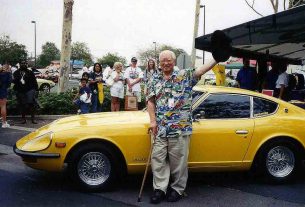変速操作不用のスクーターとは便利な二輪車だが、大メーカーのホンダ・スズキ・ヤマハには長い歴史がある。
そもそも量産の始まりは、昭和21年=敗戦翌年の1946年。貧乏にあえぐ国民のビジネスカーとして、シルバーピジョン/三菱が、次いでラビット/富士産業(現富士重工)の登場からである。
日本のスクーター市場は、しばらく二車の寡占状態だったが、1953年に新顔ジェット号/三光工業が、次いで1954年ポップスター/平野製作所、1960年ヤマハ、1961年ゲールペット/丸正自動車が登場する。スクーターは、100社を超えた二輪車とくらべて少数派だった。

さてスクーターの最盛期は昭和30年頃で、最多メーカー時代ということになる。(トヨペットクラウン登場昭和30年)
そんな市場に、ホンダ登場が1954年のこと。ホンダは新市場登場で、毎度画期的商品を投入するのが常套手段だが、スクーター市場では、ラビットとシルバーピジョンという二大巨頭を念頭に、とんでもないスクーターを開発したものだった。
ホンダ・ジュノオ号は、機構ばかりかスタイリングも斬新、だれもがビックリというスクーターだった。
諸元は、全長2070㎜・全高1025㎜。車重110kg。空冷一気筒OHV4ストローク・185cc・6.5馬力。燃費40km/ℓ。
都電10円、タクシー初乗り2キロ80円、自転車1万5000円の頃としては、ジュノオ号の18万5000円は、とても高価だった。
売り出すとパワー不足の評判が立ち、すぐに219cc・8馬力に。
このパワー不足は予想していた。ライバルより「あまり価格差が」という心配からのコストダウン目的で、既存の二輪用E型エンジン採用したのが、正直に答えを出したにすぎなかった。
開発当初の計算は、快調走行には250cc必要ということだったのだから。ちなみに8馬力になっての最高速度は時速80kmだった。
{雨が降っても濡れません}のキャッチフレーズは、二輪の常識を破る画期的なものだった。それは{コロンブスの卵}と、誰もが思ったはずである。
写真なら一目瞭然。大きな風防の上部を手前に折れば屋根になって、頭上をカバーする仕掛けだった。諸元での全高がスクーターとしては異常に高いのは、この風防のせいだったのである。
それまでのスクーターにはない、複雑なカーブで美しいボディーは、斬新なFRPだったからこそ可能だったのだ。当時FRPの成形技術は、アメリカでも確立されていない時代だった。
が、誰もが驚き感嘆したその美しさが、のちに命取りになろうとは誰も気がつかなかった。
FRPの成形は、加熱・冷却・硬化、とにかく時間を食う。生産性が悪く、月産500台分がやっとという始末では「注文しても車が来ない」が、評判を落とす一因になってしまったのだ。
また画期的なバダリーニ自動変速機にも難があり、折からの経済不況とあいまって、1955年7月で生産中止となった。
順調に育っていたら、世界的スクーターになり、輸出されて、世界中にファンが生まれたことだろうと思うと、残念至極である。